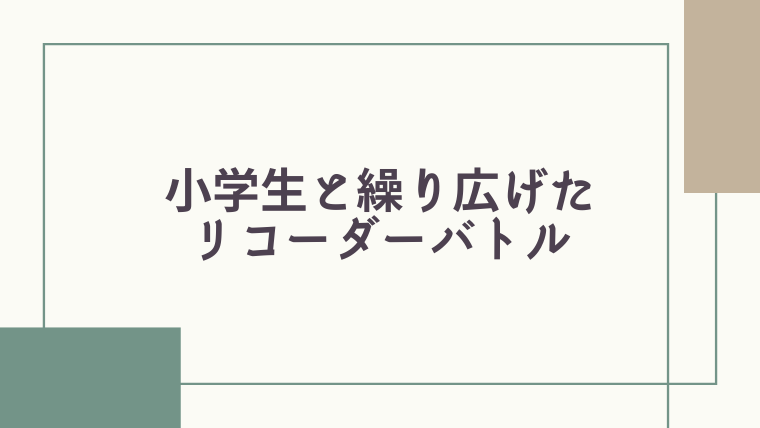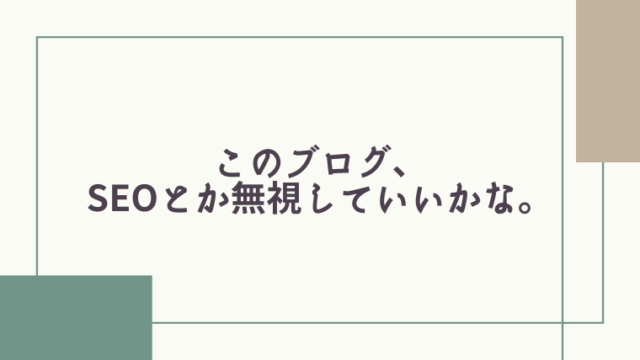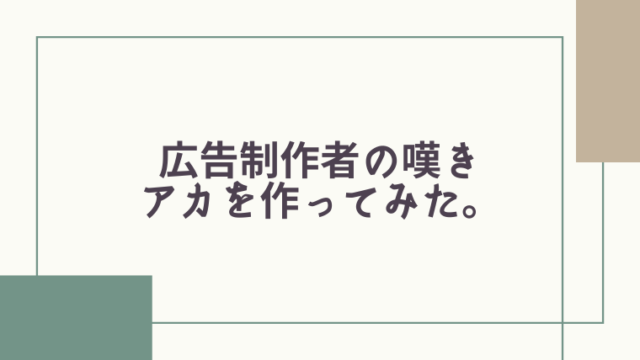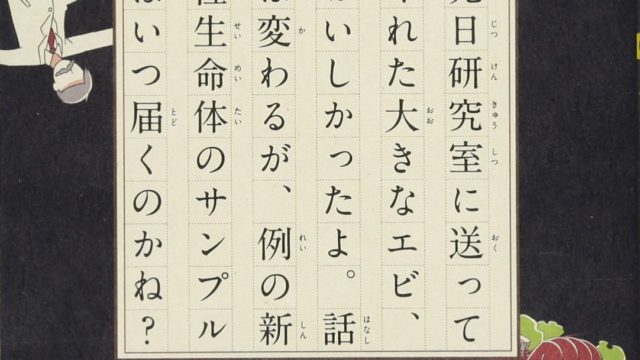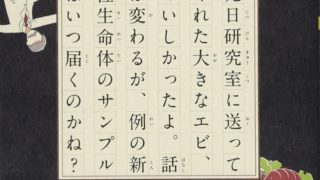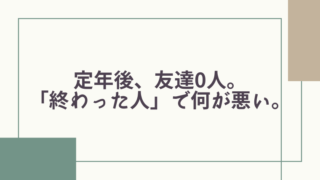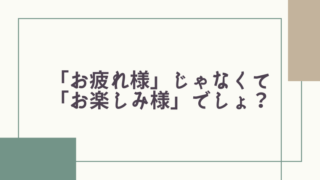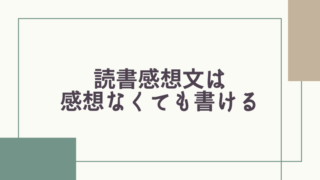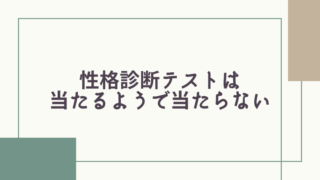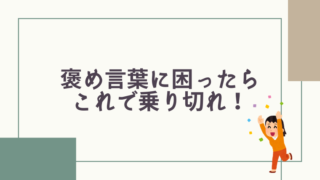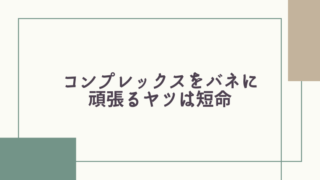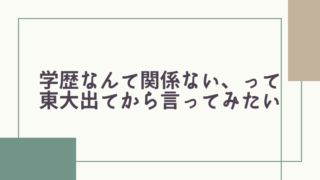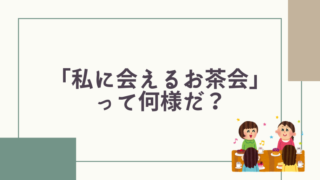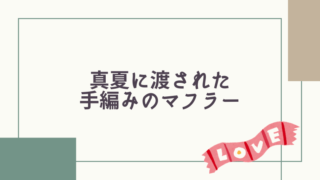「トゥートゥートゥー」
家の近所を歩いていたらどこからかリコーダーの音がしてきた。きっとどこかの家の子供がリコーダーの練習をしていたのだろう。
ああ、平和だな、私も小中学生までは吹いていたんだよな・・・そりゃ高校以上になったら吹く機会なんて基本ないもんな・・・大人になったらなんだかダサい楽器扱いされてリコーダーって本当に不憫な楽器だよな・・・
そんなことを考えながら歩いていたのだが、自分の記憶に誤りがあることに気づいた。私、大学時代にも吹いていたわと。
私の実家はマンションだ。片田舎に住んでおり、駅近ではあるが周りは田畑。子供も割と住んでいるマンションだった。治安はさほど悪くないので窓を全開にしている家が多かった。そのような土地柄というか雰囲気ではあるのでよく子供が遊んでいる声やピアノの練習音も聞こえてきた。もちろん、リコーダーも。
大学生の頃は実家に住んでいた私。そのリコーダーの音を耳にする機会は多かった。寛大な心を持つ私はテスト期間であってもああ、今日も頑張っているなと思えて聞いていたものだ。しかし、聞けば聞くほどなんだか参戦したくなってしまったのである。 「私も吹きたい!!!」
その思いが私を突き動かした。中学時代にしまい込んだリコーダーをクローゼットの奥の方から取り出し、懐かしさに浸った。ああ、これで練習したんだよなと。ただそれだけでは気が済まない。誰が吹いているのかわからぬ音色に合わせ一緒に吹きたくなってしまったのである。
家には一人。誰も私を邪魔するものはいない。そして窓を全開にし、私はリコーダーを吹き始めた。すると、その音色の主は途中から気づいたようで心なしか音を荒げながら大きな音で応酬し始めた。リコーダーバトルの始まりだ。
見知らぬ相手がリコーダーが吹いていた曲は、大概が教科書の曲だった上に、絶対音感に近い私は音を聞けば真似できる。だから聞こえてくる音をまるでインコのように追い続けた。始めは偶然だと思ったのかもしれないが徐々に向こうも気づいていったようだった。段々面白くなってきて曲の流れがわかった私はハモりを入れていくようになった。
楽しい。楽しい。とても楽しい。見知らぬ相手とリコーダーを使ってハーモニーを奏でるのだ。まるで顔が見えないのにもかかわらずメッセージを送り合う和歌のようだとも感じた。実にロマンチックだ。 しかしだ。忘れてはいけないのが、相手はおそらく小学生か中学生。しかも、その時私は大学生であり、そもそも一般的には吹かないであろうリコーダーをわざわざ取り出して見知らぬ子供とコミュニケーションをとるという時点でどうかしている。
とはいえ、なんだか面白かったのだ。何かが芽生えたわけでもないし、理由はよくわからない。だが、とにかく面白かったのだ。だから親がいない間、事あるごとに見知らぬ誰かがリコーダーを吹き始めたら、私も吹き始めるという遊びをしていた。遊びというよりもリコーダーバトルだったのかもしれない。
あの時、一緒にリコーダーバトルをしていた子供達は一体何をしているのだろう。結局どんな子だったのか全くわからない。もしかすると、恋心を抱かれていたかもしれない。「可愛いクラスのあの子が、実は自分の事が好きで一緒にリコーダーを吹いて思いを伝えているのだ」と勘違いして身悶えしていたとしたら本当に申し訳ない。
または、トラウマを植え付けていたかもしれない。リコーダーを吹くとどこからともなくリコーダーの音が聞こえてきて恐怖に打ち震えていたとしたら申し訳ない。もし『リコーダーの呪い』として学校で噂になっていたとしたら本当に申し訳ない。
そして、思いつく中で一番気味が悪いケースはリコーダーを吹いていたのが、実は小中学生ではなかったというケースだ。おじさんで、小中学生が応酬していたのだと勘違いして意気揚々とリコーダーバトルで心を通わせていたと勘違いしていたケースだ。ああ、それだとしたら、ひどい話だ。私の楽しい思い出もいとも簡単に崩れ去っていく。
しかし、この気味が悪いと思ったケース。この気味悪い張本人は自分自身だと気付いてしまった。仮にもその時『女子大生』ではあったので、運良く通報されずに済んだのかもしれない。とはいえ、今思えば、大分気味悪い存在だ。おじさんという事以外は、自分自身にあてはまるのだ。
一体あのリコーダーバトルをした子供、いや、人たちは何者だったのだろう。子供とは限らない。大人だったかもしれない。そして、私はどういう存在だったのだろうか。このように考えながら、家の近所をまた歩く。
「トゥートゥートゥー」
このリコーダーの音の主は、子供とは限らない。私のような大人である可能性もあるのだ。平和な子供の日常だと思い込んでいたものも一瞬にして気味悪い大人の非日常に大変身だ。勝手な想像をして油断してはならないのである。
「トゥートゥートゥー」
きっとどこかでまた、大人と子供の垣根を越えたリコーダーバトルが繰り広げられているに違いない。さて、私も一吹きするとするか。